皆さん、こんにちは。
大阪府堺市に拠点に店舗からオフィス、ビルなどの電気設備工事、空調設備、消防点検・保守・工事を行う松電工舎です。
将来にわたって安定的なニーズがあり、未経験からでも着実にキャリアを築けるのが消防設備士の魅力です。数ある資格のなかでも、特に取得が推奨されているのが「消防設備士甲種4類」です。
しかし、「甲種4類は難しくて合格率が低いと聞くけれど、本当だろうか?」という不安の声も耳にします。また、電気工事士としての経験を活かし、さらに消防設備のプロフェッショナルを目指したい方もいらっしゃることでしょう。
今回はそんな方々に向けて、消防設備士甲種4類のリアルな難易度や合格率、資格取得のメリット、そして合格を掴むための具体的な勉強法まで解説します。
■消防設備士甲種4類の合格率と難易度は?

まず、消防設備士甲種4類の合格率を見ていきましょう。下記のように近年の合格率はおおむね30%台で推移しています。
令和7年:39.4%
令和6年:37.2%
令和5年:32.3%
令和4年:34.4%
令和3年:37.1%
数字だけを見ると「3人に1人は受かるのか」と感じるかもしれません。しかし、見方を変えれば受験者の3人に2人は不合格となっているのが現実です。
とはいえ、国家資格の中には合格率10%未満の超難関試験も存在します。それらと比較すれば、正しいアプローチで学習すれば十分に合格が狙える「手が届く難易度」の資格だと言えるでしょう。
ただし、油断は禁物です。消防設備士甲種4類は、無対策で挑めば確実に不合格になる資格とも言われます。特につまずきやすいのが実技試験であり、筆記試験と並行して万全の準備をすることが合格のカギとなります。
そもそも、消防設備士の種類が何があるのか知りたい方はこちらをご覧ください!
》消防設備士の資格の種類は何がある?各資格の難易度や取得すべき資格を紹介!
■なぜ甲種4類の合格率は低いのか?
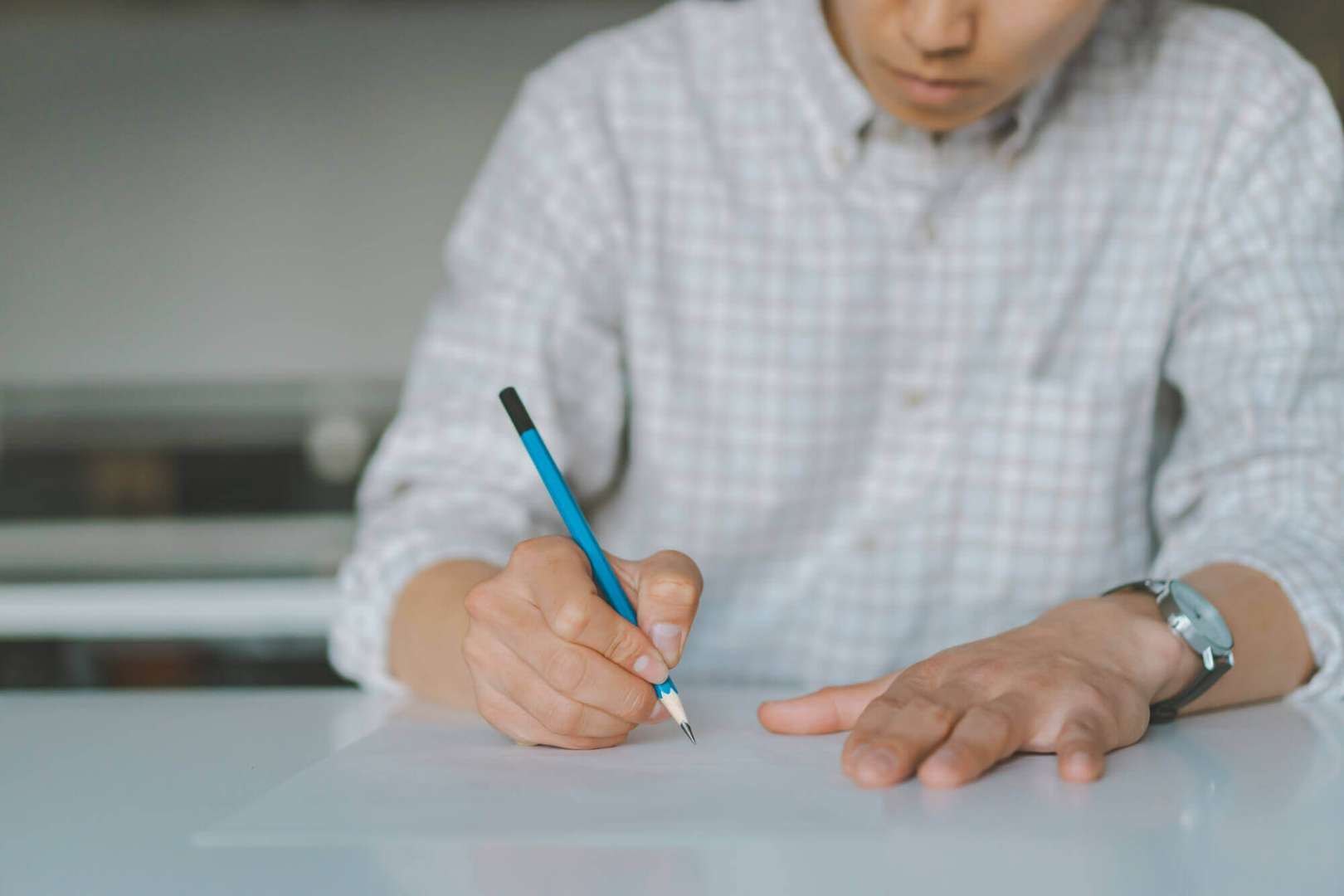
では、なぜ合格率が30%台にとどまっているのでしょうか。主な理由を2つ解説します。
・覚えるべき専門知識が膨大
甲種4類試験の特徴は、学習範囲の広さにあります。甲種4類が扱う「自動火災報知設備」には、感知器、発信機、受信機など非常に多くのタイプが存在します。それぞれに細かな構造・用途・設置基準があり、関連する消防法令の理解も不可欠です。
また、専門用語が多く、電気系の知識がない方にとっては、専門用語の多さに戸惑ってしまうことも少なくありません。加えて、設備の系統を理解し図面を読み解く力も求められるため、総合的な知識とスキルが必要になります。
・実技試験の「鑑別」と「製図」が難関
筆記試験を突破しても、実技試験が大きな壁となるケースは非常に多いです。 「鑑別」では、消防用設備機器の写真やイラストを見て、その名称・原理・用途などを記述します。「製図」では、平面図から系統図や配線図を手書きで作成します。
特に製図は、普段仕事でCADを使っている方でも注意が必要です。手書きならではのルールや記号の正確な描写に慣れておく必要があります。
■消防設備士甲種4類の難易度は他の資格と比べてどのくらい?

これから消防設備士甲種4類にチャレンジしようという方のなかには、電気・設備・建設業界における登竜門的な国家資格である第二種電気工事士を取得済みの方もいらっしゃるかと思います。
・第二種電気工事士の試験とどう違う?
電気工事士と消防設備士は、共に電気を扱う国家資格ですが、その専門領域は大きく異なります。
電気工事士は電力設備や照明、コンセントなどの「電気設備」を扱うのに対し、消防設備士は自動火災報知設備や非常放送設備といった「防災設備」が対象です。
そのため、電気工事士の資格を持っていても、消防設備士の試験では、防災機器や消防法に関する全く新しい知識を学ぶ必要があります。しかし、電気の基礎理論や配線の知識は大きなアドバンテージになることは間違いないでしょう。
・合格に必要な勉強時間
一般的に、甲種4類の合格に必要な勉強時間は「100〜200時間」と言われています。1日2時間の学習を続ければ、約2〜3カ月で合格ラインに到達できる計算です。 もちろん、これは目安であり、電気の基礎知識の有無によって必要な時間は変わります。働きながら取得を目指す方は、無理のない学習スケジュールを立てることが重要です。
こちらの記事もぜひご覧ください
》消防設備士と電気工事士はどっちがいい?資格の難易度からキャリアパスまでポイント別に徹底解説!
》消防設備点検資格者と消防設備士の違いとは?各資格の概要とどちらを取得すべきか徹底解説!
■消防設備士甲種4類を取得するメリット

・工事、整備、点検すべてを担えるスペシャリストに
消防設備士には「乙種」と「甲種」があり、甲種資格保有者だけが「工事」までを一貫して担当できるのが最大の強みです。点検・整備に加え、施工という上流工程まで携われるため、より多くの業務を任せられるようになり、現場での信頼度も高まります。キャリアの幅が一気に広がるため、電気工事士とのダブルライセンスを目指す人も増えています。
・収入アップにもつながる
資格手当を支給する企業は多く、松電工舎でも取得資格に応じて毎月手当を支給しています(2,000〜5,000円/月)。また、担当できる業務の幅が広がることは、昇給や賞与の査定においても有利に働き、着実な収入アップにつながります。
・転職時に有利に働く
消防設備士甲種4類は国家資格の中でもニーズが高く、建物管理や防災関連の企業では評価されます。経験が浅くても、資格があることで専門知識とスキルを客観的に証明できるため、転職活動においても強力なアピールポイントとなります。
》消防設備士の年収はどれくらい?年収アップのコツや取るべき資格を紹介!
》消防設備士の転職先はどんな会社がおすすめ? 転職市場や求められる人材を解説
■消防設備士甲種4類に合格するための勉強方法

では、実際に消防設備士甲種4類に合格するためのコツを紹介します。
・製図対策は“手を動かして覚える”が基本
製図問題は、参考書を眺めているだけでは絶対に対応できるようになりません。模範解答を何度も書き写し、配線本数の数え方や記号の使い方を“体で覚える”ことが大切です。普段見慣れた記号も、いざ手書きで再現しようとすると意外と手が止まってしまうものです。出題パターンを分析し、繰り返し作図練習を行いましょう。
・学習の習慣化が合格のカギ
甲種4類の試験は、独学でも合格可能とされていますが働きながら学習時間を確保するのは簡単ではありません。だからこそ「週に3日、1日1時間」など、自分のペースで学習計画を立て、それを継続することが合格への最短ルートです。通勤中の電車や休憩時間といったスキマ時間を有効活用し、アプリなどで知識を定着させるのも効果的です。
■まとめ

消防設備士甲種4類は、決して簡単な資格ではありません。しかし、正しい戦略と継続的な学習で必ず乗り越えられる壁です。特に、電気工事士としての経験をお持ちの方や、現場でのキャリアアップを真剣に考えている方にとっては、自身の市場価値を飛躍的に高める大きな武器となります。
「自分の技術をさらに活かしたい」「仕事の幅を広げて収入を増やしたい」。 そう考えるあなたにとって、甲種4類の取得はキャリアにおける大きなステップアップとなるはずです。
■松電工舎では、事業拡大に伴い電気工事士や消防設備士を募集しています!

松電工舎は大阪府堺市を拠点に、店舗やオフィスなどの電気設備工事、空調設備、防災設備工事まで幅広く手がける設備工事会社です。
現在、事業拡大に伴い、電気工事士や消防設備士、消防設備点検資格者として現場で活躍いただける方を新たに募集しています。
当社の強みは、電気・空調・消防の各分野をワンストップで対応できる総合力。大手商業施設をはじめとする多彩な現場で、実務スキルを磨きながらキャリアアップを目指せる環境です。
原則土日休みで、平日の残業もほとんどありません。プライベートを大切にしながら、休日出勤でしっかり稼ぐといった柔軟な働き方も可能です。社内には多様な背景を持つ仲間が在籍し、一人ひとりが自分らしく働ける職場づくりを目指しています。
業務に必要な資格の取得費用は会社が全額負担。働きながら安心してスキルアップできる資格取得支援制度も完備しています。さらに、当社が推奨する資格を取得した場合は、毎月2,000円〜5,000円の資格手当も支給されます。
先行きが見えにくい社会にあって、信じられるのは自分のスキルです。 私たち松電工舎で、そのスキルをさらに磨き、自分らしいキャリアを築いてみませんか? ご応募を心よりお待ちしています。
▼関連記事▼
》消防設備士はやめとけって本当?きついと言われる理由や向いている人の特徴を紹介!
》消防設備士にとってのホワイト企業とは?特徴や見分け方のポイントを紹介
》消防設備点検資格者1種・2種の違いとは?資格区分や取得するメリットを紹介!
》消防設備点検資格者の年収は?年収アップのためにできることやキャリアプランを紹介!
》消防設備工事のプロが教える!消防設備点検と防火対象物点検の違いとは?


