皆さん、こんにちは。
大阪府堺市を拠点に店舗からオフィス、ビルなどの電気設備工事、空調設備、消防点検・保守・工事を行う松電工舎です。
消防設備の点検や整備、設置などを行うためには、国家資格である「消防設備士」が必要です。しかし、消防設備士には多くの種類があるため、「どの資格を取得すればいいのか」「難易度に違いがあるのか」など、不安や疑問を抱える人も多いでしょう。
この記事では消防設備士の資格について、各資格の概要や難易度について解説します。おすすめの取得順についても解説するので、消防設備士の資格取得をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
■消防設備士は大きく分けて2つ

消防設備士の資格には大きく分けて2つの種類があり、それぞれ担当できる業務の範囲が異なります。ここではそれぞれの種類の概要を解説します。
・甲種|点検・整備・工事ができる資格
甲種は、消防設備の点検や整備、設置、交換工事を行える資格です。取り扱える消防設備は特類と1類から5類までの、計6つの区分に分類されます。甲種は点検や整備に加えて「消防設備の設置や交換工事ができる」という点が乙種との大きな違いです。
・乙種|点検・整備ができる資格
乙種は、消防設備の点検と整備を行える資格です。取り扱える消防設備は1類から7類まで7つの区分に分類されます。乙種は消防設備の点検と整備のみを行える資格なので、設置や交換工事は行えません。
■消防設備士の種類は何がある?

甲種は特類のほか第1類から第5類の6つ、乙種には第1類から第7類の7つの区分があり、それぞれ取り扱える消防設備が異なります。ここではそれぞれの区分で取り扱える消防設備を紹介します。
・甲種特類
特類とは、特殊消防用設備のことを指します。従来型とは違った特殊な消防設備で、従来型が設置できないケースなどにおいて代替として設置される場合が多いです。点検や整備をする際にも高い専門性が必要になります。
・甲種・乙種第1類
第1類は、主に水を使用する消防設備のことを指します。具体的には、屋内消火栓設備や屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備などが該当します。
・甲種・乙種第2類
第2類は、主に泡を使用する消防設備のことで、油類や危険物の火災など、水での消火に適さない場所で使用されます。具体的には、泡消火設備やパッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備などが該当します。
・甲種・乙種第3類
第3類は、ガス消火設備のことを指します。具体的には不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備などの特殊消火設備が該当します。
・甲種・乙種第4類
第4類は、主に火災報知器などの設備のことを指します。具体的には自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備などが該当します。
・甲種・乙種第5類
第5類は、主に避難に使用する消防用設備のことを指します。具体的には金属製避難はしごや救助袋、緩降機などが該当します。
・乙種第6類
第6類は、消火器のことを指します。消火器は工事をするという概念がないため、乙種のみに該当します。
・乙種第7類
第7類は、漏電火災報知器のことを指します。漏電火災報知器の工事は「電気工事士」の資格が必要なため、消防設備士は点検のみを行います。
■消防設備士の難易度(合格率)は?

令和6年(4月〜10月)の消防設備士試験の合格率は、甲種全体で29.4%、乙種全体で37.8%、消防設備士試験全体では33.6%でした。全体的に、甲種よりも乙種のほうが比較的合格率が高い傾向にあります。
甲種で最も合格率が高かったのは、特類の32.8%でした。ただし、特類はそもそも受験資格のハードルが高く、甲種の3種類以上の免状交付が必要なため、決して難易度が低いとはいえないでしょう。甲種で最も合格率が低かったのは、第1類の23.7%でした。
また、乙種で最も合格率が高かったのは第7類の61.5%、最も合格率が低かったのは第3類で24.8%でした。
参考資料:一般財団法人 消防試験研究センター「試験実施状況」
■どの資格から取得すべき?
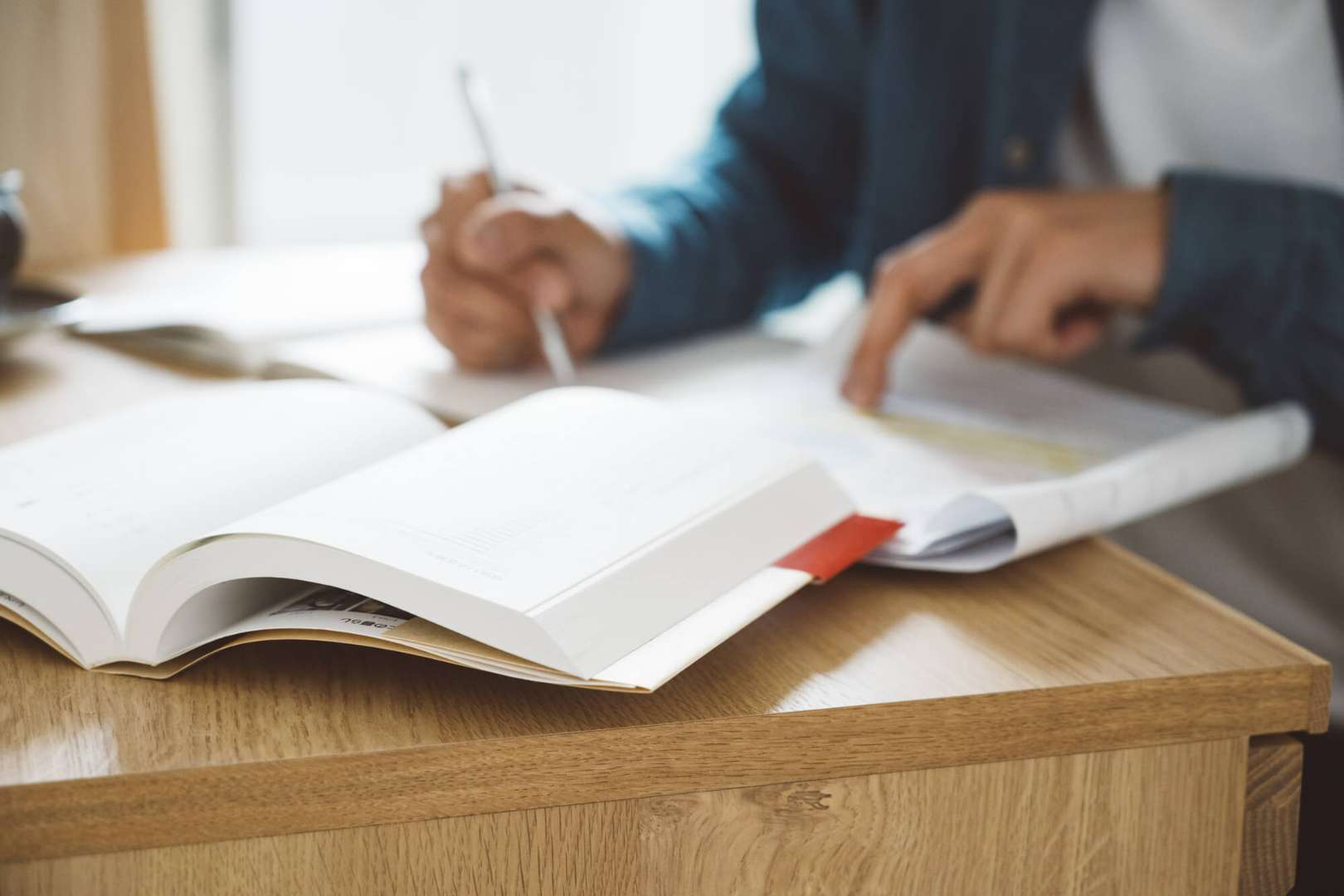
消防設備士の資格のなかでは、最初に取得するのは乙種第6類がおすすめです。乙種第6類は消火器を取り扱える資格であり、消火器は消防法によって多くの建物に設置義務があるため、需要も非常に多いです。
乙種第6類は、令和6年(4月〜10月)の消防設備士試験のなかで最も受験者数が多く、18,987人が受験しています。合格率も36.9%と、他の類と比べると比較的高いほうです。
乙種は特別な受験資格がなく、年齢や学歴、職歴などを問わず誰でも受験が可能であり、とくに第6類はほかの類に比べて試験範囲が狭いため、短期間の学習でも合格を目指しやすいでしょう。
■乙種第6類に合格した後は?

乙種第6類に合格したら、次は甲種・乙種の第4類の取得を目指すのがおすすめです。第4種は火災報知器を取り扱える資格であり、消火器と同様に多くの建物に設置されていることから、需要が高い資格といえるでしょう。
ただし、その前に「第二種電気工事士」の資格を取得しておくのがおすすめです。電気工事士の資格を取得すると、甲種消防設備士試験の受験資格をクリアできます。火災報知設備は電気とも関連性が高いため、電気工事士の資格をもっていると実務にも役立つため、このタイミングで取得できるとよいでしょう。
第二種電気工事士を取得できれば、乙種ではなくいきなり甲種第4類を受験することも可能です。
また、次に取得するのであれば、甲種第1類もおすすめです。消火栓やスプリンクラーも火災報知器と同様に需要が高い設備であるため、活躍の場が広がるでしょう。
■まとめ

消防設備士には甲種と乙種があり、乙種は消防設備の点検や整備のみを行えるのに対して、甲種はさらに設置や交換工事も行えるという違いがあります。さらに甲種は6つ、乙種は7つの区分に分類され、それぞれ取り扱える消防設備が異なります。
消防設備士の資格を取得する目的を明確にし、必必要な資格を取得するために、計画的に準備を進めましょう。
■松電工舎では、事業拡大に伴い電気工事士や消防設備士を募集しています!

弊社は大阪府堺市を拠点に、店舗やオフィスなどの電気設備工事・空調設備・防災設備工事を手掛けている会社です。
弊社では事業拡大に伴い、電気工事士・消防設備士・消防設備点検者として一緒に働いてくださる方を募集しております。弊社は弱電工事だけでなく、計装工事・消防設備工事など幅広い業務ができるほか、大手商業施設の施工実績もあるため、スキルアップやキャリアアップを目指せます。
また、弊社は自身の生活スタイルに合った働き方ができる環境です。原則土日を休日として、平日はほぼ残業がありません。プライベートを重視したい方は自身の生活に時間を使えるように土日に休み、稼ぎたい方は休日に働いてがんばった分だけ還元されるようにするなど、希望に合わせて働ける環境が整っています。
弊社は外国人や女性社員も在籍しております。また、個人事業主から正社員への採用実績もあり、個人事業主として働いていた方のご応募も大歓迎です。
資格や免許の取得支援もあり、取得にかかる費用は全額会社負担となっています。また、弊社で推奨している資格をひとつ取得するごとに2,000円〜5,000円/月の資格手当もあります。
電気工事士の資格を活かしたい方や、これから消防設備士や消防設備点検者として活躍したい方は、ぜひ松電工舎で一緒に働いてみませんか?
▼関連記事▼
》消防設備士の転職先はどんな会社がおすすめ? 転職市場や求められる人材を解説
》消防設備士の年収はどれくらい?年収アップのコツや取るべき資格を紹介!
》消防設備士にとってのホワイト企業とは?特徴や見分け方のポイントを紹介
》消防設備工事のプロが教える!消防設備点検と防火対象物点検の違いとは?
》消防設備点検資格者と消防設備士の違いとは?各資格の概要とどちらを取得すべきか徹底解説!
》消防設備点検資格者1種・2種の違いとは?資格区分や取得するメリットを紹介!


