皆さん、こんにちは。
大阪府堺市を拠点に店舗やオフィス、ビルなどの電気設備工事、空調設備、消防点検・保守・工事を行う松電工舎です。
資格の取得を検討する際に、「消防設備士と電気工事士のどちらの取得を目指したらいいか」「難易度はどのくらいなのか」など、疑問や不安を抱えている人もいるでしょう。どちらの資格も建物や設備の工事には欠かせないものですが、それぞれの資格を取得することで携われる仕事内容や今後のキャリアには大きな違いがあります。
この記事では、資格の取得を検討している方に向けて、消防設備士と電気工事士のそれぞれの資格の概要や試験内容、難易度などについて解説します。建設業界でスキルアップを目指したい方や転職希望者はもちろん、未経験者にもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
■消防設備士と電気工事士の仕事内容と働き方の違い

消防設備士と電気工事士について、それぞれの仕事内容や働き方の違いについて解説します。
・消防設備士
消防設備士とは、消防法に基づき、施設に設置されている消防設備の点検・整備などをするために必要な国家資格です。学校や病院、ホテル、商業施設などのさまざまな建物において、消防法に規定された消防設備の点検や整備などを行います。
消防設備士の資格には甲種と乙種があり、甲種の取得者は消防設備の点検・整備のほか、設置・交換作業を行えます。乙種の取得者は消防設備の点検・整備のみを行い、設置・交換作業は行えません。
また、甲種には特類から5類、乙種には1類から7類まであり、それぞれ取り扱うことのできる消防設備が異なります。たとえば1類であれば、屋内消火栓設備や屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備を取り扱うことが可能です。
消防設備士の資格を取得すると、消防設備会社やビル管理・メンテナンス会社、防災関係の会社などで活躍することが可能です。
・電気工事士
電気工事士は、電気設備の工事を行うのに必要な国家資格です。主な仕事は、建設物の電気設備の設計や施工を行う「建設電気工事」と、鉄道に係る電気設備の施工や保守業務を行う「鉄道電気工事」があります。
電気工事士の資格には第一種と第二種があり、第二種は一般住宅や小規模な店舗・事業所、家庭用太陽発電設備など、600ボルト以下で受電する設備の工事を行えます。第一種は第二種の範囲に加え、最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事を行うことが可能です。
電気工事士の資格を取得すると、電気工事会社や建設会社、ビル管理・メンテナンス会社などで活躍できます。
■資格取得の難易度と試験内容の違い
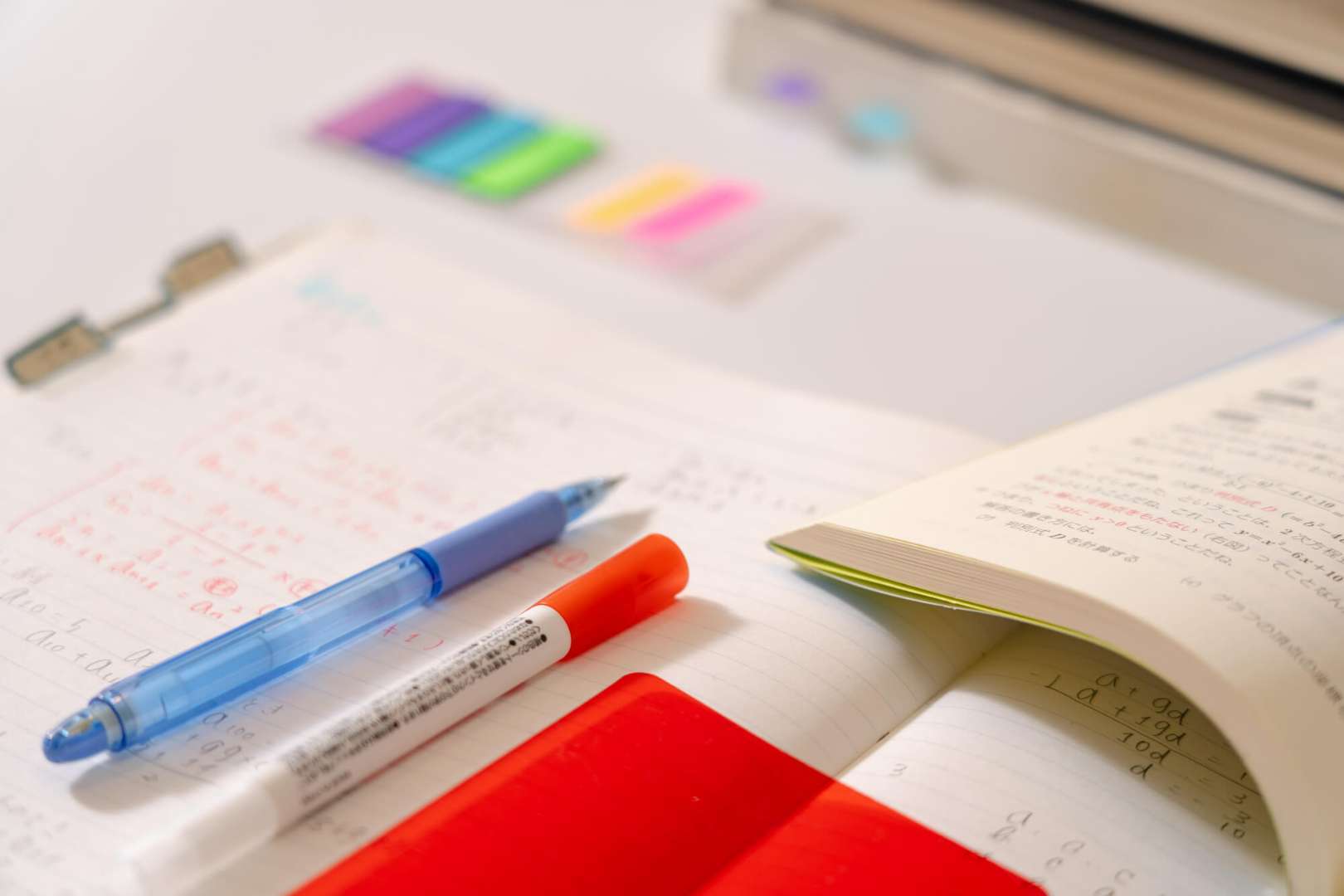
消防設備士と電気工事士のそれぞれの資格について、難易度や試験内容について解説します。
・消防設備士試験の特徴
消防設備士は甲種と乙種があり、消防試験研究センターの統計によると、甲種の合格率は30〜40%、乙種は50〜60%程度となっています。比較的高い水準にあり、基礎知識をしっかり身につけることで十分合格を目指せます。甲種と乙種、どちらも筆記試験と実技試験があります。
消防設備士試験は、乙種については特別な受験資格はなく、誰でも受験可能です。甲種については指定された資格または実務経験をもっていること、または大学や高校等での特定の学科を修めていることが条件となっています。
》消防設備士の資格の種類は何がある?各資格の難易度や取得すべき資格を紹介!
・電気工事士試験の特徴
電気工事士は第一種と第二種があり、学科試験と技能試験の両方に合格することで取得できます。学科試験の合格率は、第一種が40~50%程度、第二種が50~60%程度、技能試験の合格率は、一種・二種ともに60~70%程度とされています。また、学科試験は四肢択一形式です。
電気工事士試験は特別な受験資格はなく、年齢や学歴の制約もありません。ただし、第二種については高校生レベルの数学知識(四則演算、指数、三角関数など)が求められます。特に公式の応用力や計算の正確性が重要です。
》電気工事士2種は何ができる?資格の特徴や取得方法を解説
■消防設備士、電気工事士それぞれのキャリアパスと将来性

消防設備士と電気工事士のそれぞれについて、キャリアパスと将来性について解説します。
・消防設備士のキャリアパス
消防設備士は、現場技術者として経験を積んでいくことで、現場管理として昇進することが可能です。消防設備士は、甲種が特類〜5類、乙種が1類〜7類まであります。資格の種類が多いため、最低限必要となる資格以外については、仕事で必要になるものからその都度取得していく流れでよいでしょう。
防災意識の高まりを背景に、消防設備士は建物管理や消防設備関連企業での需要が増加しています。特に商業施設や公共施設での活躍が期待されています。
》消防設備士の年収はどれくらい?年収アップのコツや取るべき資格を紹介!
・電気工事士のキャリアパス
電気工事士は、まずは第二種を取得して一般住宅や小規模な店舗などの工事を担当しながら経験を積み、第一種の取得を目指すとよいでしょう。
第一種の取得後はビルや工場などの工事も担当できるため、幅広く経験を積み、施工管理を目指すのが一般的なキャリアパスです。また、管理職や経営層を目指すのではなく、専門職を極めるというキャリアパスもあります。
電気工事士は、再生可能エネルギーやスマートホーム技術の普及に伴い、太陽光発電システムやIoT対応設備の導入に携わる機会が増えています。これにより、長期的なキャリアの安定性が期待できます。
》電気工事士2種の資格を活かせる仕事とは?キャリアパスとおすすめ職種を徹底解説!
》電気工事士の次に取るべき資格は何? キャリアアップにおすすめの資格を紹介
》電気工事士の年収はいくら?平均年収や年収アップのポイントを紹介!
■消防設備士と電気工事士、どちらを選ぶべきか?

消防設備士と電気工事士の資格取得で迷っているのであれば、最初に第二種電気工事士の資格から挑戦するのがおすすめです。第二種電気工事士の資格を保有していると、消防設備士の甲種第4類において免除科目があるため、効率的に資格の取得が目指せるでしょう。
第二種電気工事士から取得し、将来的にはどちらも取得するのがおすすめです。消防設備士と電気工事士の両方を取得すると、電気設備工事会社や消防設備メーカー、ビル管理・メンテナンス会社などで幅広く重宝される存在となるでしょう。
■まとめ

消防設備士と電気工事士は、いずれも需要の高い資格であり、それぞれ異なる専門分野での活躍が可能です。まずは比較的取り組みやすい第二種電気工事士の資格取得を目指し、実務経験を積む中で消防設備士や第一種電気工事士へのステップアップを検討すると良いでしょう。
■松電工舎では、事業拡大に伴い電気工事士や消防設備士を募集しています!

弊社は大阪府堺市を拠点に、店舗やオフィスなどの電気設備工事・空調設備・防災設備工事を手掛けている会社です。
事業拡大に伴い、電気工事士・消防設備士・消防設備点検者として一緒に働いてくださる方を募集しております。
弊社は弱電工事だけでなく、計装工事や消防設備工事など幅広い業務に対応しているほか大手商業施設の施工実績もあるため、さまざまな業務を経験しながらスキルアップやキャリアアップを目指すことが可能です。
弊社は原則として土日を休日としており、平日もほぼ残業はありません。プライベートを重視したい方は土日に休み、逆に稼ぎたい方は休日に働くことができる環境です。がんばった分だけ還元されるような体制を整えておりますので、自身の生活スタイルに合った働き方が実現できます。
外国人や女性社員も在籍しているほか、個人事業主から正社員への採用実績もありますので、個人事業主として働いていた方も大歓迎です。
資格や免許の取得支援もあるため、たとえば「電気工事士の資格はもっているけど、消防設備士の資格はまだもっていない」という方も、働きながら資格取得を目指せます。資格取得にかかる費用は全額会社負担で、さらに資格手当もあるため、弊社で推奨している資格のうちひとつ取得するごとに2,000円~5,000円/月の補助もあります。
電気工事士や消防設備士としての経験がある方をはじめ、消防設備士については未経験の方も大歓迎ですので、ぜひ弊社で一緒に働いてみませんか?
▼関連記事▼
》高齢化が進む建設業界の今後10年はどうなる?将来性や電気工事業界がおすすめな理由を紹介
》電気工事士になるにはどうしたらいい? 未経験から活躍するための実務経験の積み方を紹介!
》電気工事士はやめとけと言われるのはなぜ? 就職するメリットや向いている人の特徴を紹介
》消防設備士にとってのホワイト企業とは?特徴や見分け方のポイントを紹介
》電気工事士におすすめの就職・転職先とは? 会社選びのポイントを紹介!


