大阪府堺市に拠点に店舗からオフィス、ビルなどの電気設備工事、空調設備、消防点検・保守・工事を行う松電工舎です。
火災のリスクを未然に防ぎ、万が一の際には迅速な対応を可能にする消防用設備。これらの設備が適切に機能するかを確認する「消防設備点検資格者」は、ビルメンテナンスや建築関連業界で重要な役割を担っています。実はこの資格、1種・2種・特種といった区分があり、どの資格が自分に最適なのか悩む方も多いのではないでしょうか?
本記事では、1種と2種の資格内容や役割の違いをはじめ、取得するメリットやキャリアへの影響を徹底解説。自分に合った資格選びのポイントや、取得後の活用法についてもわかりやすくご紹介します。消防設備業界でキャリアを築きたい方や、さらにスキルアップを目指す方に向けて、ぜひ参考にしてください。
■消防設備点検資格者とは?

消防設備点検資格者は、ビルや施設に設置された消防用設備を定期的に点検・管理し、万が一の火災に備えて設備が正常に機能する状態を保つための専門職です。この資格は国家資格に位置づけられており、専門的な知識と技術が必要とされます。火災時には迅速な初期対応が求められますが、そのために消火器や火災報知器、スプリンクラー、非常用照明などの設備が確実に作動することが重要です。そのため、これらの設備は定期的な点検や維持管理が法律で義務づけられています。
・消防設備点検資格者の役割
消防設備点検資格者の役割は、消防設備が正常に機能するかどうかを確認することです。具体的には、以下のような業務を担当します:
設備の点検・検査:消火器の圧力確認やスプリンクラーの作動チェック、火災報知器の異常がないかを確認します。
不具合の報告と修理提案:点検の際に不具合が発見された場合には、早急な修理や交換を提案し、設備が常に適切に稼働できるようにします。
点検記録の作成:点検作業の結果は、法令に基づいて報告書として記録され、管理者やオーナーに提供されます。この記録は消防署への報告の際にも重要な役割を果たします。
・消防設備点検の重要性
消防設備点検資格者は、こうした消防設備の定期点検を通じて設備が適切に機能するかを確認し、不具合があれば修理や交換の必要性を明確にします。消防設備が適切に設置・維持されていなければ、火災の初期段階で迅速な対応ができず、被害が拡大するリスクが高まります。
また、点検結果を報告書として記録し、施設管理者やオーナーが防火体制をしっかり整えるための支援を行います。このように、消防設備点検資格者は火災時に万全な初期対応が可能になるよう、重要な役割を担っているのです。
》消防用設備点検をしないとどうなる? 点検が必要な施設や実施頻度をわかりやすく解説!
■消防設備点検資格者には3つの資格区分がある
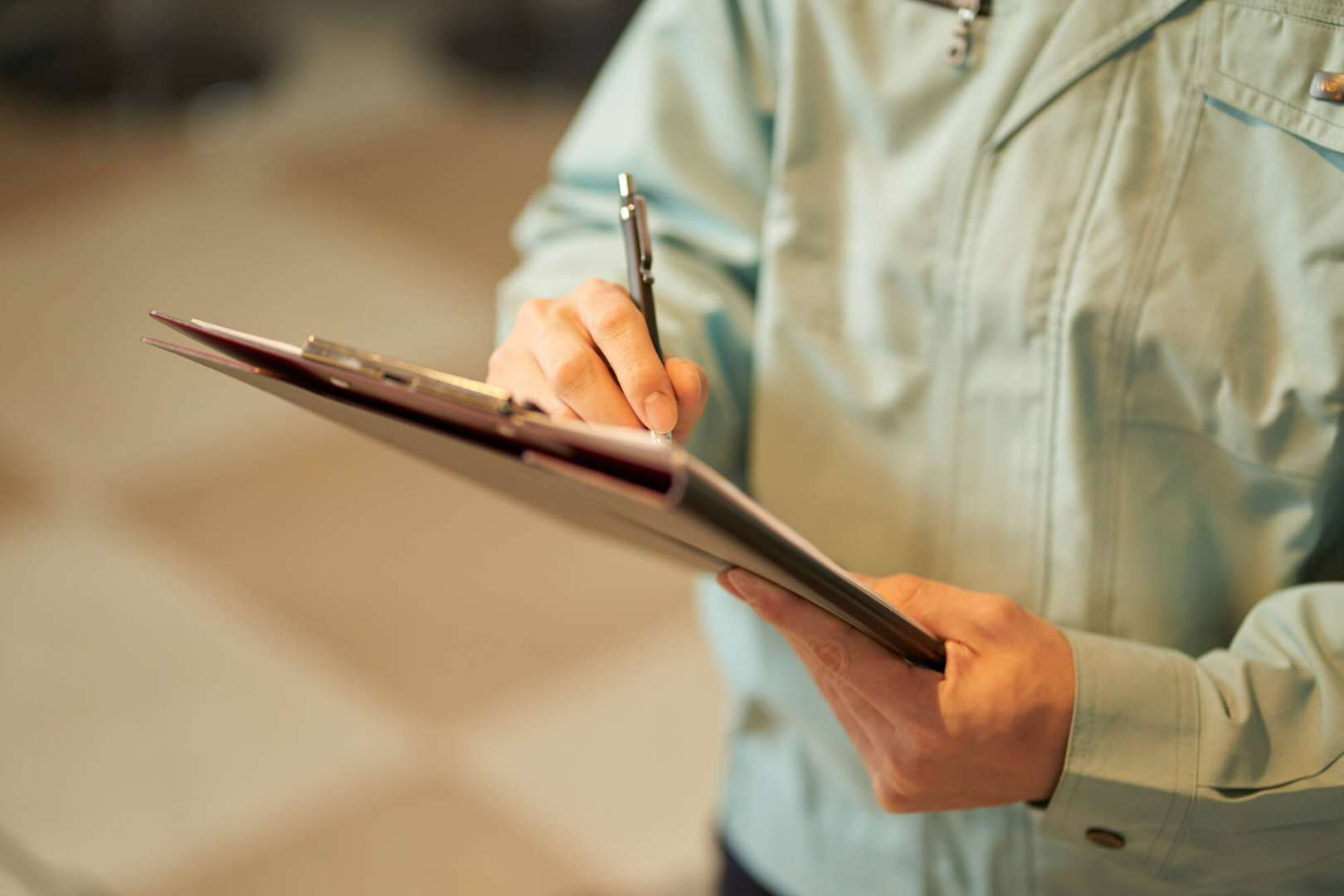
消防設備点検資格者には、「第1種消防設備点検資格者」「第2種消防設備点検資格者」「特種消防設備点検資格者」の3つの区分が存在します。それぞれの資格は、点検可能な設備の種類や業務内容が異なり、建物の規模や設備の種類に応じて必要な資格も異なります。以下に、それぞれの資格区分について詳しく説明します。
・第1種消防設備点検資格者
第1種消防設備点検資格者は、ビルや商業施設、工場などの大規模な建物に設置される高度な消防設備の点検を行える資格です。この資格を取得すると、スプリンクラー設備や自動火災報知設備、消火設備など、幅広い防火・消火設備の点検が可能になります。第1種資格は、幅広い設備に対応できることから、資格取得にはより高度な知識と技術が求められます。
また、第1種資格保有者は、建物の火災リスクや防災計画の重要な部分を担い、点検業務を通して消防設備の安全性を確保します。そのため、大規模施設や商業施設などで高い需要があり、ビルメンテナンス業界や消防点検業者でも重宝される資格です。
・第2種消防設備点検資格者
第2種消防設備点検資格者は、主に小規模な建物や一般住宅の消防設備を点検するための資格です。例えば、住宅用火災警報器や簡易的な消火設備など、比較的基本的な消防設備の点検ができるようになります。この資格は、ビルやオフィスのビルメンテナンス業務に携わる方や、規模の小さな建物を管理する方にとって有用です。
第2種資格は第1種と比較すると点検対象が限定されており、技術的な難易度もやや低いため、資格取得も比較的容易です。しかし、住宅や小規模施設の消防設備点検を担う立場として、防火対策に貢献できる責任ある資格であることに変わりはありません。
・特種消防設備点検資格者
特種消防設備点検資格者は、通常の消防設備とは異なる特殊な設備の点検を行うための資格です。特に化学工場や石油関連施設など、高度な防火・消火対策が必要な施設に設置される特殊設備が点検対象となります。特殊な施設では火災時のリスクも大きいため、点検に際しては高度な専門知識が不可欠です。
※特殊消防用設備は、一般的なビルや住宅に設置される設備とは異なり、特に危険性の高い環境や、火災発生時のリスクが大きい施設で用いられます。たとえば、化学物質を扱うプラントや石油施設など、爆発や大規模な延焼の危険がある施設では、通常の消火設備では不十分な場合があります。そのため、特定の化学物質に対応したガス消火設備や、高温環境にも対応できる耐熱性の高い消火システムが必要です。
この資格は、限られた専門分野での需要があり、一般的なビルや住宅ではあまり見られませんが、化学プラントや危険物を扱う施設などの安全管理の現場では非常に重要です。特種消防設備点検資格者は、こうした専門施設において、施設の安全を支える重要な役割を果たしています。
■消防設備点検資格者1種と2種の違い

消防設備点検資格者の1種と2種は、点検できる設備の種類や業務の範囲が異なるため、それぞれ異なるスキルや知識が求められます。ここでは、1種と2種の具体的な違いについて、点検可能な設備の範囲、資格取得の難易度、講習内容の3つの観点から解説します。
・点検可能な設備の違い
まず、1種と2種の資格は、点検できる消防設備の範囲が違います。
第1種消防設備点検資格者は、ビルや工場、商業施設など、大規模な建物に設置される複雑で高度な消防設備の点検ができます。たとえば、スプリンクラー設備や屋内・屋外消火栓設備、消火器などの消火設備などが含まれます。これらの設備は、火災時に多くの人命を守るために重要であるため、正確な点検が求められます。
第2種消防設備点検資格者は、主に住宅や小規模な建物に設置された基本的な消防設備の点検ができます。対象となるのは、住宅用火災警報器や避難器具、誘導灯など、火災を知らせる設備や避難するための設備です。大規模なビルで見られるような複雑な設備には対応しませんが、住宅や小さな店舗の安全確保に重要な役割を果たします。
1種資格は幅広い設備をカバーするため、さまざまな施設での活躍が期待されますが、2種資格は住宅や小規模な施設向けの業務に特化しているといえます。
1種の資格を取得すれば消火器のほか、スプリンクラー設備や屋内消火栓の点検もできるようになります。
これに対し消防設備点検資格者2種とは、火災を知らせる設備や避難するための設備の点検を実施するための資格です。
2種の資格取得後には火災報知設備や避難器具、誘導灯といった設備の点検が可能となります。
・資格取得の難易度
資格取得の難易度も1種と2種で違いがありますが、どちらも講習と修了試験に合格することで取得できます。試験の合格率は90%以上と高いため、しっかり勉強すれば多くの人が合格できます。
第1種消防設備点検資格者の合格率は2021年で約95.9%、2020年で約94.6%と高く、講習と試験に集中して取り組めば十分に取得可能です。ただし、点検の対象が複雑な設備を含むため、試験にはより専門的な内容が含まれます。
第2種消防設備点検資格者の合格率は2021年で約97.3%、2020年で約96.3%と、1種よりさらに高く、比較的取得しやすい資格です。点検対象が基本的な設備に限られているため、内容も比較的理解しやすいとされています。
どちらの資格も、講習で学んだことをしっかり理解すれば合格しやすい資格といえます。
・講習内容の違い
消防設備点検資格者講習の内容は1種と2種で多少異なります。
講習で学ぶ内容も、それぞれ異なります。
第1種の講習では、ビルや工場など大規模施設に設置される高度な設備の仕組みや点検方法、火災時のリスク管理について学びます。設備の構造や作動の仕組みも詳しく習得するため、幅広い知識が求められます。例えば1種の講習では非常電源や配線に関する内容、消火栓設備の点検方法などを詳しく学びます
第2種の講習では、住宅や小規模な建物の基本的な設備の点検方法を学びます。火災警報器や消火器といったシンプルな設備を対象に、基本的な点検手順や火災時の基本知識を習得します。これに対し2種の講習では非常電源や火災報知器に関する知識を多く学ぶことになります。ただし、火災予防概論や点検制度、法規など、一部共通している科目もあります。
消防設備点検資格者取得の際には、講習日程や講習内容をよく確認しておきましょう。
■消防設備点検資格者の資格を取得するメリット

消防設備点検資格者の資格取得には以下のようなメリットが考えられます。
・点検に必要な資格なので需要が高い
消防設備点検資格者の資格は、消防法に基づき、ビルや施設に設置された消防用設備の点検を行うために必須の資格です。消防用設備は定期的に点検を行う必要があり、特に大規模施設や商業ビルでは欠かせません。この資格を持つことで、消火器や火災報知器などの基本的な設備だけでなく、スプリンクラー設備や泡消火設備といった高度な設備の点検も担当することができます。1種の資格を持つと、特にビル管理業界や商業施設などで高い需要があり、求人数も多く、専門職として安定した仕事に就ける可能性が高まります。
さらに、点検業務はビル管理会社や設備会社にとって法律で義務付けられた業務です。そのため、資格を保有することは企業にとってもメリットが大きく、資格取得者に対して資格手当を支給する企業も多いです。資格があれば、安心して働ける環境が整うことも期待できます。
・キャリアアップが見込める
消防設備点検資格者の資格は、将来的なキャリアアップにおいても大きな役割を果たします。例えば、1種と2種の資格を組み合わせて取得すると、住宅から大規模施設まで幅広い点検業務を担当でき、より多くの現場経験を積むことが可能です。これにより、点検業務の専門家としてだけでなく、防火管理のプロフェッショナルとしての知識や経験が評価され、企業内で管理職やリーダー職への昇進が期待できます。
また、消防設備点検の業務は、他の関連資格との組み合わせによってさらに活用の幅が広がります。たとえば、「消防設備士」や「防火管理者」の資格と合わせて取得すると、消防設備の点検業務だけでなく、設置や工事、修理にも携わることができ、さらなるキャリアアップが見込めます。こうしたスキルの幅を広げることは、現場での信頼を得るだけでなく、長期的なキャリア形成にもプラスになります。
》消防設備点検資格者と消防設備士の違いとは?各資格の概要とどちらを取得すべきか徹底解説!
■まとめ

消防設備点検資格者は、建物や施設の安全を守るために欠かせない国家資格です。1種は大型施設や高度な消防設備、2種は住宅や小規模施設、特種は化学工場などの特殊設備の点検が可能で、それぞれ異なる役割を担います。
この資格を取得することで、ビル管理や防災の専門職としてキャリアアップや収入アップが期待できるだけでなく、社会的にも貢献度の高い仕事に就くことができます。
スキルを身につけて活躍したいとお考えなら、ぜひ消防設備点検資格者を目指してみましょう。
■松電工舎では、事業拡大に伴い消防設備士や消防設備メンテナンススタッフを募集しています!

松電工舎では大阪府堺市を拠点に、店舗やオフィスなどの電気設備工事・空調設備・防災設備工事を手掛けている会社です。
事業拡大に伴い、電気工事士・消防設備士・消防設備点検者として一緒に働いてくださる方を募集しております。
入社時は消防設備士などの資格は必要なく、徐々に仕事を覚えながら資格を取得していただきます。資格および免許の取得支援制度があり、費用は全額会社負担のため、お金の心配をせず勉強に励むことが可能です。
また、研修体制も充実しています。1人で作業することはなく常にグループで行動し、経験豊富な先輩が指導しますので、未経験でも問題ありません。大手商業施設などの施工依頼も多く、現場の仕事を通じて飛躍的なスキルアップが望めます。
そのため、真面目で規則を守れる方や礼儀正しい方、体力に自信のある方、そして成長する意欲のある方は、どなたでも大歓迎です。実際に未経験で入社して現場管理をしている社員もいる他、女性社員や外国人社員も活躍しています。
もちろん、業界経験者や有資格者は経験と能力に見合った待遇でお迎えし、個人事業主(一人親方)として働いていた方も歓迎いたします。個人事業主から正社員への採用実績もありますので、ご希望の方はぜひご相談ください。
さらに、労働環境の整備にも力を入れており、土日は原則として休日で、平日はほぼ残業がありません。プライベートを重視したい方は土日に休み、逆に稼ぎたい方は平日休み・土日出勤するなど、自分に合った働き方が可能です。
もちろん、がんばりはしっかり評価して給与に反映させている他、資格手当などの福利厚生も充実。弊社で推奨している資格を1つ取得するごとに、2,000円~5,000円/月を補助しています。
働きやすい環境で専門的なスキルを身につけ、社会を支え将来性もある仕事をしてみませんか? 興味がある方はお気軽にご連絡ください。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております。
▼関連記事▼
》消防設備工事のプロが教える!消防設備点検と防火対象物点検の違いとは?
》消防設備士の転職先はどんな会社がおすすめ? 転職市場や求められる人材を解説
》消防設備士の年収はどれくらい?年収アップのコツや取るべき資格を紹介!
》消防設備士にとってのホワイト企業とは?特徴や見分け方のポイントを紹介
》高齢化が進む建設業界の今後10年はどうなる?将来性や電気工事業界がおすすめな理由を紹介


