皆さんこんにちは。大阪府堺市を拠点に、電気設備工事・空調設備工事・防災設備工事を手掛けている松電工舎です。
個人でお仕事をされている方にとっても、大きな影響がでてくる「インボイス制度」が2023年10月からスタートされます。なんとなく不安を煽られるような報道が続く中、制度自体の概要や自分たちにどういった影響があるのかははっきりわからず、今後の対応に不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、「インボイス制度ってどんなこと?」「登録がいるみたいだけど、自分も該当するの?」「なんのことかわからない単語が多すぎる!」「結局、自分にどんな影響があるの?」といったインボイス制度に関する疑問について解説します。
■インボイス制度とは
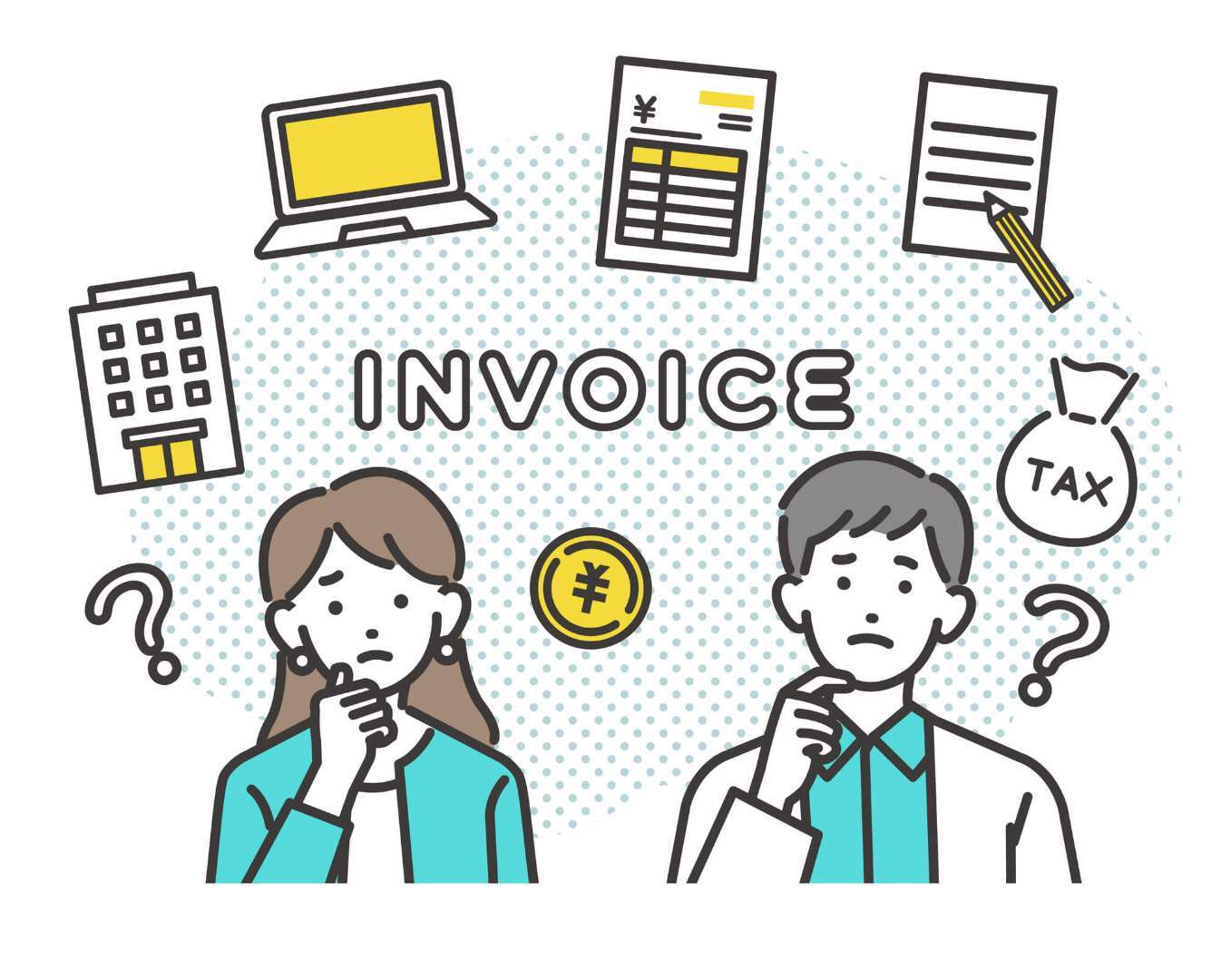
インボイス制度導入後は、仕入れ先がインボイスを発行しなければ、仕入れ税額控除が受けられなくなります。
分かりやすく言い換えると、
インボイス制度とは、取引する会社の中でどこが消費税を負担するかを押し付け合う制度です。インボイス(国が公認した請求書)がある場合は、請求する側が負担、インボイスがない場合は、請求される側が負担します。
これによって、これまで免税措置を受けていた個人で働く小規模事業者のほとんどが大きな影響をうけます。
参考|国税庁-インボイス制度の概要
■インボイス制度で出てくる用語

インボイス制度について調べていると、出てくる用語について解説します。
・インボイス
従来の請求書に税率と税額を正確に伝えるために必要事項を追加した請求書のことです。
正式名称は「適格請求書」といいます。
・免税事業者
2年前の売り上げが1000万以下の事業者です。消費税が免除されます。インボイスを発行することはできません。
・課税事業者
2年前の売り上げが1000万以上の事業者で、消費税を納める義務があります。
・インボイス発行事業者
インボイスの登録を申請した事業者です。
登録すると仕入れ税額控除をするのに必要なインボイスを発行できます。
課税事業者すべてが、インボイス発行事業者となるわけではなく、申請と登録が必要です。
逆に言い換えると、課税事業者であってもインボイス登録が必須ではありません。
課税事業者とインボイス発行事業者は混同しやすいので注意が必要です。
■「課税事業者」と「免税事業者」と「インボイス発行事業者」のメリットとデメリット

・免税事業者のメリットとデメリット
【メリット】
・消費税を納税する必要がない
・従来通りの請求書類を使える
【デメリット】
・インボイスを発行できる下請会社に乗り換えられて、取引先が減る可能性がある
・実質的に、消費税分の値引きを求められる可能性がある
・課税事業者のメリットとデメリット
【メリット】
・インボイス発行事業者の登録申請が可能
【デメリット】
・消費税の納税義務がある
・インボイス発行事業者のメリットとデメリット
【メリット】
・取引先に消費税を押し付けることがないので、従来通りの良好な関係が保てる
【デメリット】
・請求書のフォーマットを変更する必要がある・・・請求書に登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額 の記載追加が必須となります。
・経理処理システムを使っている場合、インボイス対応のものに入れ替える必要がある
・請求書類の保管方法を見直す必要がある
■インボイス制度に対応しないとどうなる?

取引先が免税事業者のままでいることを選択し、インボイスを発行できない場合、課税事業者は仕入れ税額控除を受けられません。
そのため、課税事業者はできるだけインボイスを発行できる課税事業者と取引した方が節税になります。
例えば…
課税事業者(発注者)が「課税事業者A」(工事会社)と「免税事業者B」(あなたのような個人事業主)とそれぞれ取引をしていると想定します。
課税事業者Aとの取引では、仕入れ税額控除を受けられるため、自社の利益分に対する消費税のみを負担します。
しかし、免税事業者Bはインボイスを発行できないため、課税事業者は仕入控除を受けられません。その結果、免税事業者Bが負担するはずだった消費税を押し付けられてしまいます。
そのため、発注者の立場からすると、インボイスを発行できる事業者と取引した方が節税になり利益が増えます。
■まずは課税事業者か免税事業者か確認しよう!

自分が「課税事業者」なのか「免税事業者」なのかを確認しましょう。
それぞれのケースでどのような流れでインボイス制度に対応するのかを解説します。
・自社がすでに課税事業者の場合
登録申請を行うだけで適格請求書発行事業者になれるため、インボイスを発行できます。
取引先とも現状維持できる可能性が大きいです。
・自社が免税事業者の場合
メリットデメリットを考えて、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかを選択しなければなりません。
主となる取引先が免税事業者や個人の場合は、現状のまま免税事業者でいる方がお得です。
しかし、取引先が課税事業者である場合、インボイスの発行を求められるケース、実質的な消費税相当額の値下げ要求、取引中止となるケースも考えられます。
独占禁止法に抵触するため、インボイスが発行できないことを理由としたあからさまな値下げ強要や不当な取引中止はできません。しかし、説明方法や話し方を変えているだけで、発注者としては、「押し付けられた消費税分を解消できなければ、このまま取引をつづけることは難しい」と考えています。
売り上げが1000万円以下の「免税事業者」の会社でも、消費税の申告をすれば「課税事業者」になることができます。課税事業者になるとインボイス発行事業者の申請も可能です。ただし、課税事業者となると、これまで免除されていた消費税の支払いが必須です。取引先との関係性やどういった打診があるかによって、インボイスの発行事業者となるかどうかの決断を迫られます。
■インボイス制度は建設業界の一人親方にどんな影響がある?今後どうしたらいい?
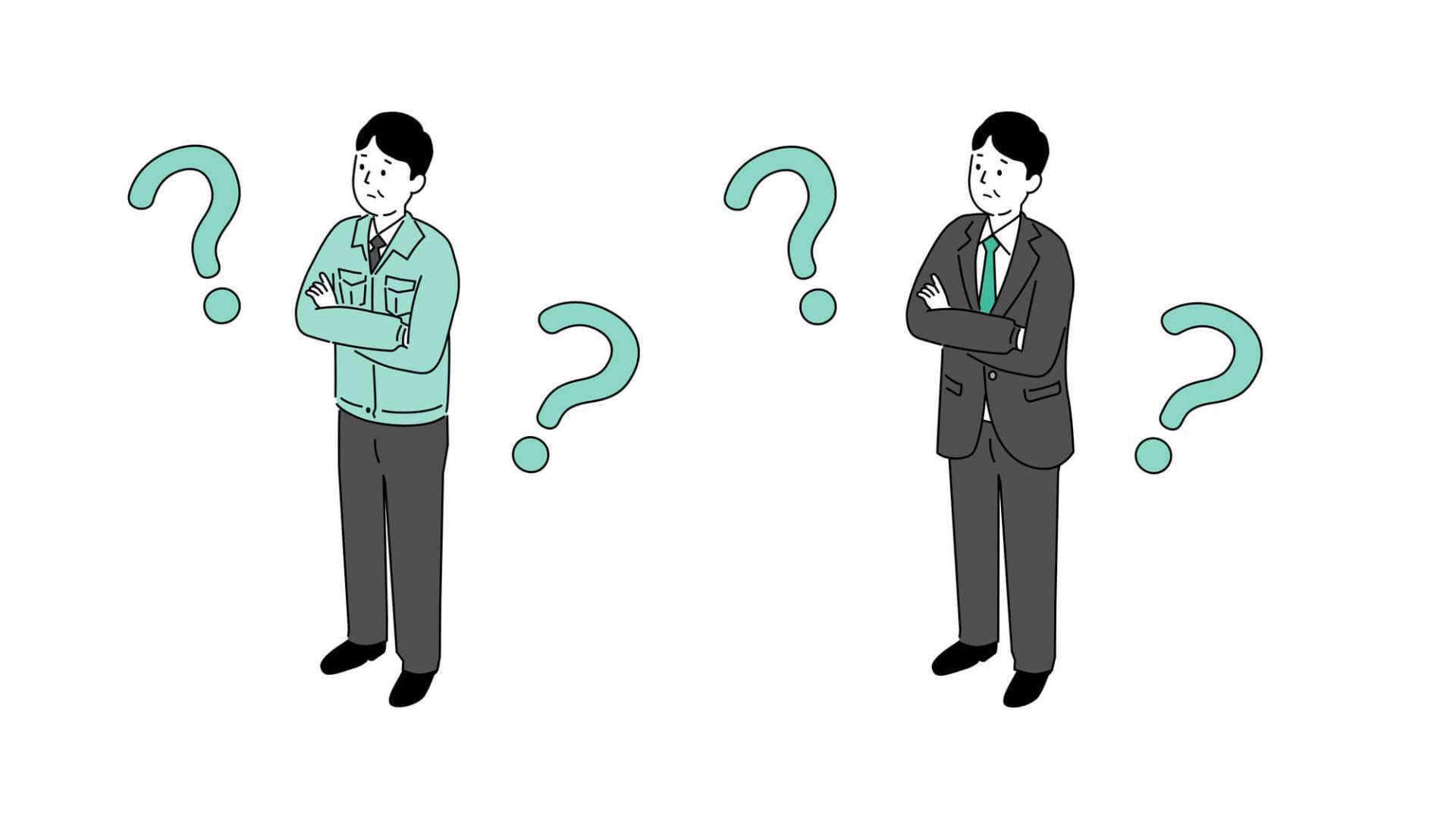
建設業界では、一人親方として働いている方にとって直接どんな影響があるのかについて解説します。
・一人親方はどんな影響がある?
課税事業者の場合と免税事業者の場合それぞれについてメリットとデメリットを紹介します。
① 元々、課税事業者の場合
【メリット】
・今まで免税事業者に流れていた仕事を、大量に奪い取れるチャンスがある
・免税事業者との取引を見直した新規取引先との間では、単価アップを見込める
【デメリット】
・適格請求書発行者の申請の手間がかかる
・事務処理や保管書類が増加する
② 免税事業者として続けていく場合
【メリット】
・登録申請の手間がかからない
・売上が下がらなければ現状の収入を維持できる
【デメリット】
・インボイスを発行できる業者へ取引先を取られる可能性がある
・発注側は税を負担したくないため、消費税分の値引きを求められる可能性がある
③ 免税事業者から課税事業者へ変更する場合
【メリット】
・現在の取引を継続できる可能性が高い
・免税事業者を続ける職人から、仕事を大量に奪い取れるチャンスがある
【デメリット】
・消費税負担により、収入が減ってしまうので、経営が難しい場合は、取引先と単価アップの打ち合わせが必要となる
・単価アップが見込めない場合、単価に見合う新しい取引先を探す手間がかかる
・事務処理量が格段に増加して、時間もかかる
・今後どうしたらよいのか?
今後は、インボイス発行事業者となるかを判断する必要があります。下記の内容について検討しましょう。
① 取引先の課税事業者と免税事業者の割合や取引額の割合を確認する
現状、課税事業者との取引額の割合が多く、発注者から打診があった場合は、取引継続のためには課税事業となりインボイスを発行することが避けられません。
② 収支と自社の資金的な体力を確認する
収入が減った場合の生活への影響と大きな出費のタイミングはいつかを検討しましょう
③ 事務作業の増加に対応できる体制が整えられるか検討する
取引先がインボイスを必要としているかの確認、インボイス請求書類記載内容の増加、保管書類の増加、記帳内容の増加、端数処理の方法の変更、簡易課税制度を利用する場合はそれぞれの取引の消費税額のチェックなど煩雑な作業が大幅に増加します。ご自身で事務処理をしている場合、まとまった時間を確保が必要です。
大きなポイントとして、上記3つを検討したうえで、免税事業者でいるか、課税事業者となってインボイス発行事業者の申請をするかを決定します。
3つすべてに該当する場合は、課税事業者となるのがおすすめですが、検討を重ねても、なかなかどちらを選ぶのがお得なのか決められない場合も考えられます。
収益減についてももちろん問題ですが、取引先との関係や事務処理負担の増加も大きな問題です。
その中で、一つの選択肢として、経験やスキルを活かせる会社へ正社員として就職する方法も考えられます。ひとり親方として現場を仕切る力や問題解決をする力を持ち、即戦力として活躍できる人材は貴重な存在として、企業からも求められています。
■松電工舎では現在、電気工事士・消防設備士・管工事士として一緒に働いてくださる方を募集しております。

社員になってしまうと時間の自由がきかなくなる心配もあるかと思いますが、希望に沿った勤務体系を実現しています。事務作業や取引先との条件打合わせといった煩わしい部分については、全て当社で行いますので、不要な時間を使う必要もなくなります。
働きやすい環境、風通しの良い職場で、更なるスキルアップも目指せますので、あなたの豊富な経験や現場スキルをぜひ当社で活かしていただけませんか?
また、希望される勤務条件についてご相談いただければ、前向きに検討させていただきます。
興味のある方は、ぜひ一度当社までお問い合わせください!ご連絡お待ちしております!
▼関連記事▼
》電気工事って何をする仕事? 松電工舎での働き方や魅力を紹介
》電気工事士はやめとけと言われるのはなぜ? 就職するメリットや向いている人の特徴を紹介
》電気工事士が必要な理由とは?将来性と松電工舎でのキャリアプランを紹介


