皆さんこんにちは。大阪府堺市を拠点に、電気設備工事・空調設備工事・防災設備工事を手掛けている松電工舎です。
働く人の「希望する働き方」やライフワークバランスを実現するため「働き方改革」への取り組みが進められています。建設業界では、年間300時間以上の残業が日常化していることも多く、長時間労働の規制や週休2日制の導入が難しいとされてきました。
ついに2024年3月から建設業界でも「働き方改革」が全面施行されます。建設業界に携わる人は、これまでの働き方と比べてどのような変化があるのかについてわかりやすく説明します。
■建設業の2024年問題とは?

「働き方改革」とは、2019年4月に施行されました。時間外労働時間上限の設定、有給休暇取得の義務化、フレックス制度の導入などが主な内容です。
トラックドライバー、医療従事者と同様に、建設業界は今までの勤務形態や業界の内情を踏まえて「すぐに制度の導入に踏み切ることが難しい業種」とされ、2024年3月まで5年間の猶予期間が設定されました。
制度導入が難しい業種とされた理由としては、労働者の高齢化や労働人口の減少に伴う人材不足を長時間労働でカバーすることが常態化していることや、日当で働いているため休んだ分だけ手取りが減るため、休みを取りたがらない意識が根強いといった労働環境があげられます。
「働き方改革関連法」が適用開始される2024年4月までに建設業界が解決しなければならない労働環境問題のことをまとめて「建設業の2024年問題」と呼ばれています。
■建設業の現状は?

建設業界の現状について、データを関係省庁のデータに基づいて説明します。
・人材不足
建設業就業者数は、2020年は約492万人で、ピーク時である1997年の約685万人と比較して28%(約190万人)減少しています。
また、就業者の年齢別でみると、55歳以上の割合が約36%、29歳以下の割合が12%です。
他の業界も含めた全産業の割合は、55歳以上の割合が約31.1%、29歳以下の割合が16.6%であることと比べても建設業界の高齢者の割合の高さがわかります。
就業者数のピークである1997年は、55歳以上の割合が約24.5%、29歳以下の割合が約22%でした。
就業者数の減少と合わせて考えると、若年層の新規就業が減少していることや、若年層の退職数が増えていることがわかります。
2016年時点でのデータによると、電気工事士を含む建設業界全体で60歳以上の高齢者の割合は約24.5%、人数にすると約81.1万人です。1947年~1949年生まれの団塊の世代が75歳以上となることを考慮すると、3~10年後には大量離職が見込まれています。
ベテランの就業者が培ってきた技術が継承できず失われてしまうことが大きな問題となっています。
・長時間労働
建設業の年間の平均労働時間は、1985時間です。全産業の平均は1621時間のため、年間にすると360時間以上の長く、約1.2倍の時間就業しています。
また、年間の平均出勤日数においても、建設業は平均244日、全産業は212日です。他産業では4週8休(週休2日)が当たり前となっていますが、建設業全体でみると約40%が4週4休(週休1日)以下で就業しています。
出典:
国土交通省 最近の建設業を巡る状況について【報告】令和3年10月15日
国土交通省 建設業及び建設工事従事者の現状
■建設業の2024年問題によってなにが変わる?

建設業界では2024年4月1日から適用される「働き方改革関連法」に向けて、長時間勤務や休日の問題を含む労働環境についての問題解決が必要とされています。
この建設業の2024年問題を解決するために、国土交通省は「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、建設業界に向けて働き方改革を実現するための具体的な施策を提案しています。
働き方改革施行後、どのように変わっていくのか、具体的に紹介します。
・週休2日制の導入や適正な工期設定
公共工事において週休2日の実施件数を拡大することからはじめて、民間工事でも週休2日の拡大を図っていきます。具体的には、工期設定を長くとることと工期が伸びた分だけ増える経費を計上することです。
工期設定については、災害復旧工事や工期に制約がある工事を除いて、これまで4週6休相当で換算していた工期を週休2日対象工事へ見直す取り組みが始まっています。
工期の延長に伴い、これまでと比較して労務費、重機の賃料、仮設費、現場管理費といった経費を、現場閉所の状況に応じて必要係数を掛けて計上することとしています。
・ICTなどの新技術により生産性の向上
ICTとは、建物を作るための調査、設計、施工、アフターフォロー、修繕までの一連の流れにおいて、効率化や生産性向上に役立てる情報通信技術のことです。
多くの建設関連企業がICTの活用や人材育成に取り組める環境を整えるため、積算基準の改善や、書類の簡素化などの省力化や監督、検査の合理化を推進しています。国土交通省の各地方整備局でもICT施工に取り組む事業者向けのサポートやアドバイスを受けられる「ICTサポート制度」が整備されています。
そういった背景をもとに、タブレットによるペーパーレス化やウェアラブルカメラの活用などIOT技術を活用しながら施工品質の向上と省力化を図る、入札時や施工時の必要書類の内容を改定して書類作成負担を軽減するなど簡素化する動きがすすめられています。
また、積算基準を改定し、ICTの稼働実態に応じた積算を可能とし、一般管理費率等を細心の実態を踏まえて見直ししています。
出典:国土交通省 建設業働き方加速化プログラム
■これからの時代、電気工事士はどうなの?

ここまで説明した変化によって、今後電気工事士の仕事はどのように変化していくことが考えられるかについて紹介します。
・給与等の待遇が改善される
高齢化による廃業などで業者数や就業者数が減少しても。需要数は変わらないため、続けている業者へ集中して仕事量が増加することが考えられます。
需要はあるものの、電気工事を含む建設業全体で、団塊世代の大量離職による深刻な人手不足は避けられません。それにより建設業就業者は重用され給与などの待遇も改善されていくことが予想されます。
・労働環境が改善される
「働き方改革」の導入により、これまでのように無理な工期設定に合わせて過酷な労働条件を強いることができなくなります。
残業時間の上限の設定や時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。そのため今後は、労働時間や休日取得を考慮した工期の設定や、施工の平準化を進めて、繁忙期と閑散期の労働時間の差をなくし、一年を通して安定して働ける環境となります。
・電気工事士を目指す人が増加
電気工事士を目指すための国家資格である「第二種電気工事士試験」の受験申込者数は、近年、大幅に増加する傾向にあります。令和3年度には過去最高の20万人を突破しました。
人気が高まっている理由として考えられるのは下記の通りです。
◆人材不足によって需要が集中するため、活躍の場が拡大すること
◆電気工事業界はITの発達により、業界自体の今後の成長が見込めること
◆人材不足に伴い、売り手市場となって賃金アップが予想されること
◆働き方改革によって必然的に働きやすい環境整備の整備がなされること
◆AIの普及が進んでも、なくなることのない専門職であること
◆合格率が40%前後で推移しており、国家資格の中ではとりやすい資格であること
◆電気工事資格は、資格を持っている人だけが作業できる「業務独占資格」であること
◆将来的に独立が可能なこと
電気工事士の将来性や松電工舎でのキャリアプランについては、下記のブログで詳しく説明しておりますので、合わせてご覧ください。
》電気工事士が必要な理由とは?将来性と松電工舎でのキャリアプランを紹介
■まとめ
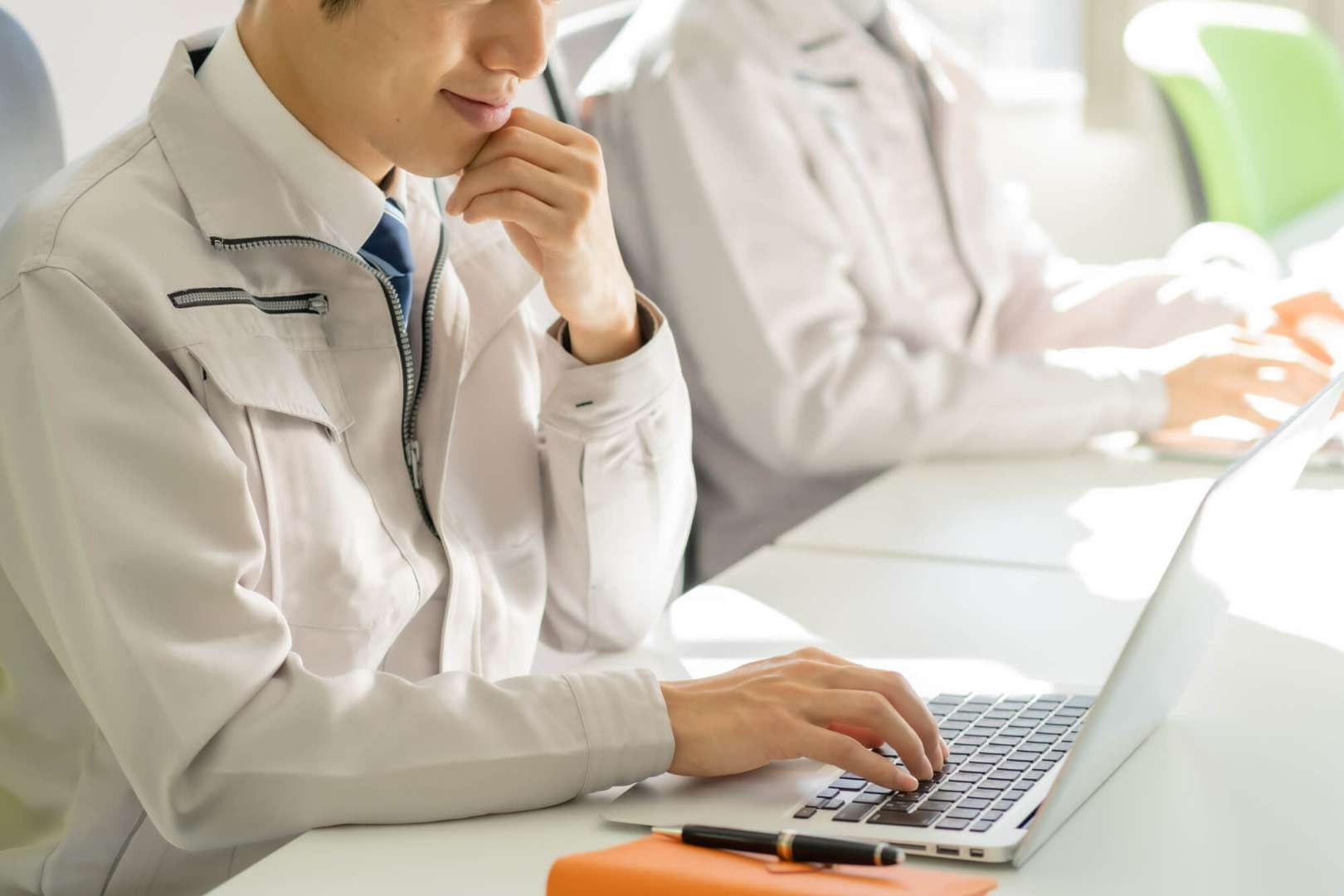
2024年問題が建設業界に与える影響や建設業界の現状、働き方改革がどのような影響を及ぼすのかについて解説しました。
以下にポイントをまとめます。
・建設業界の高齢化問題は深刻で、団塊世代の離職時期が迫っていると考えられること
・人手不足によって売り手市場となり、仕事量の増加や待遇改善が見込まれること
・働き方改革によって、休日や労働時間など職場環境の整備がすすめられること
・電気工事士は、ITの発達により活躍の場が広がっている将来性のある仕事であること
・上記の理由により、電気工事士を目指す人が大幅に増えていること
2024年問題は建設業にとって解決すべき点が多くある大きな課題です。これまで常態化してきた元請会社の無理のある工期設定を、現場の労働者の長時間労働でカバーするといったしわ寄せをなくし、適正な工期を設定することが求められます。解決するためには多くの点で見直しや意識の改革が必要です。しかし、建設業界で働く人にとっては、働きやすい環境やライフワークバランスの重視へ向けた整備が進むので、今までのキツイ仕事であるイメージとはちがった働き方ができます。
■多くの人が注目している電気工事士として、松電工舎でいっしょに働きませんか?

松電工舎は大阪府堺市に拠点に店舗からオフィスなどの電気設備工事、空調設備、防災設備工事を行う会社です。
業界初心者の方も大歓迎です。外国人や女性社員も在籍し活躍しています。
丁寧な指導と相談しやすい環境を大切にしているので、先輩に教わりながらスキルを蓄えていくことが可能です。また、資格取得支援制度も整えているため、入社前に資格を所持している必要はありません。実際の現場で作業を覚えながらの取得を応援します。
また、個人事業主として働いていた方も、ぜひこれまで培った技術や知識を私たちに貸してください。経験やスキルに応じた待遇をお約束します。
これまでの施工実績も豊富で、大手商業施設の施工経験もあります。経験者の方でもスキルアップが望める環境です。
その他、社員のプライベートを大切にしたいと考えているので、平日の残業はほとんどなく、希望に合わせた休日取得が可能です。原則、土日が休日ですが、要望や予定に合わせて曜日変更も可能です。
風通しがよく、社員を大切にする職場で、一緒にスキルアップを目指しませんか?興味をお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせください!
▼関連記事▼
》電気工事って何をする仕事? 松電工舎での働き方や魅力を紹介
》電気工事士はやめとけと言われるのはなぜ? 就職するメリットや向いている人の特徴を紹介
》インボイス制度は電気工事士の個人事業主にどんな影響が?わかりやすく解説します


